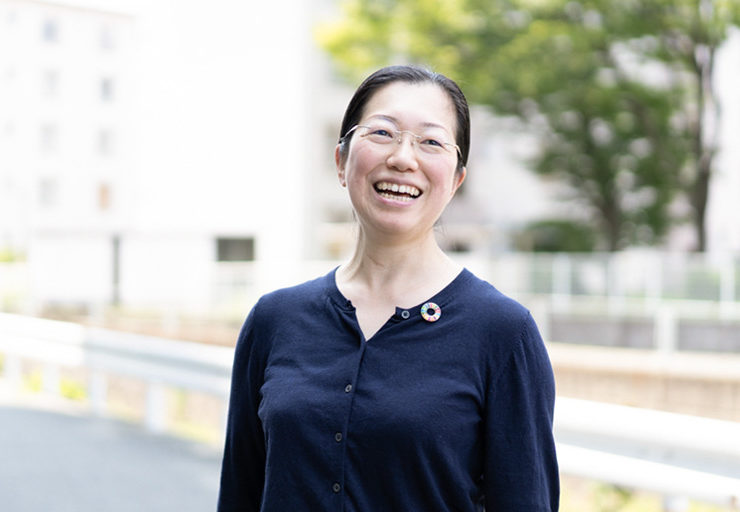敷地環境調査士

敷地環境調査
- 敷地調査で特に重要だと考えているポイントは?
- 敷地調査の際にまず確認するのは、上下水道や電気といったインフラが整っているかどうかです。これがきちんとしていないと、思わぬ費用が発生してしまうこともあるからです。
また、周辺環境を見るうえで特に意識しているのが、隣家の窓の位置や高さ。これは、実際に住み始めたときにプライバシーや日当たり、風通しなどに大きく影響します。些細に見えるこの配慮が、ご近所との良好な関係にもつながると思うんです。
最近は5mの高所カメラを活用して、空間を立体的に把握できるようになり、何も建っていない土地でも、家が建った後のイメージをお客様と共有しやすくなりました。敷地調査は“その土地を読む”こと。丁寧に調べることで、設計や暮らしの質にしっかりつながると信じています。 - これまでに調査した中で特に印象に残っている土地は?
- 印象的だったのは、ある大型分譲地の測量です。広々とした土地に、これからどんな家々が並んでいくのかを想像するのが、とてもワクワクしました。
私にとってはどの土地も唯一無二。一つひとつ違うからこそ、毎回真新しい気持ちで調査に向き合っています。そして、その都度得た経験や気づきを次の調査に活かしていく。この積み重ねが、お客様にとっての安心につながると感じています。
例えば、敷地の形状や隣接する土地との高低差、日照や風通しなど、同じ土地はとありません。どの調査も単なるルーティンではなく、「ここに住まう人の暮らしの土台を整える」大切な仕事として向き合っています。 - 敷地調査をしっかり行うことでどんなメリットがありますか?
- 敷地調査を丁寧に行うことで、建物の設計だけでなく外構や造成の計画もぐっと立てやすくなります。例えば以前、調整区域内の広大な土地で、南北に高い間知ブロックがあり、自由な土地の形状変更が難しいケースがありました。その際には、敷地全体を少し斜めに造成することで、見事に高低差をクリア。なんと100〜130もの測定ポイントを計測して、最適な形を導き出しました。
高低差は建物だけでなく、外構や排水計画にも影響します。最初にしっかり調査することで、後々のトラブルや想定外の出費を防ぎ、お客様の大切な家づくりを支えることができる。まさに「調査は家づくりの土台」と考えています。 - 調査をするうえで「ここは絶対に見逃さない!」というポイントは?
- まず確認するのはインフラが整っているかどうか。特に上下水道や雨水の排水、電気の送電経路などは、整備状況や引き込み工事の有無によって費用が大きく変わるため、注意深く調べます。
現地ではオートレベルという機器を使って、高低差をミリ単位で正確に測定。どんなに広い敷地でも、地面の起伏や傾斜をしっかりとデータ化して設計チームに渡します。
調査は1人で行うことが多いため、バッテリーの予備や機材のチェックも欠かせません。時には1日がかりの作業になることもありますが、「この調査がいい家につながる」と思えば、どんな大変さも苦になりません。家づくりの見えないところまでしっかり支えたいと思っています。 - お客様が土地を選ぶ際に気を付けるべきことは?
- 土地選びでまず注目してほしいのは、やはりインフラが整っているかという点。そして日々の暮らしやすさに直結する、前面道路の幅や車の交通量も大切なポイントです。
最近では、福岡でも都市部の土地の価格高騰により、40坪を下回るような敷地も増えてきました。そうした中でも日当たりや風通しを確保するには、敷地の向きや周囲の環境をしっかりと見極める必要があります。
私は建物の設計は専門ではありませんが、季節による日の出や日没の方向、風の通り道まで調べて、より良い家づくりに役立つ情報を調査票に落とし込んでいます。可能であれば、朝・昼・夕・夜と、時間帯を変えて土地を見ていただくと、暮らしのイメージがより具体的になると思います。